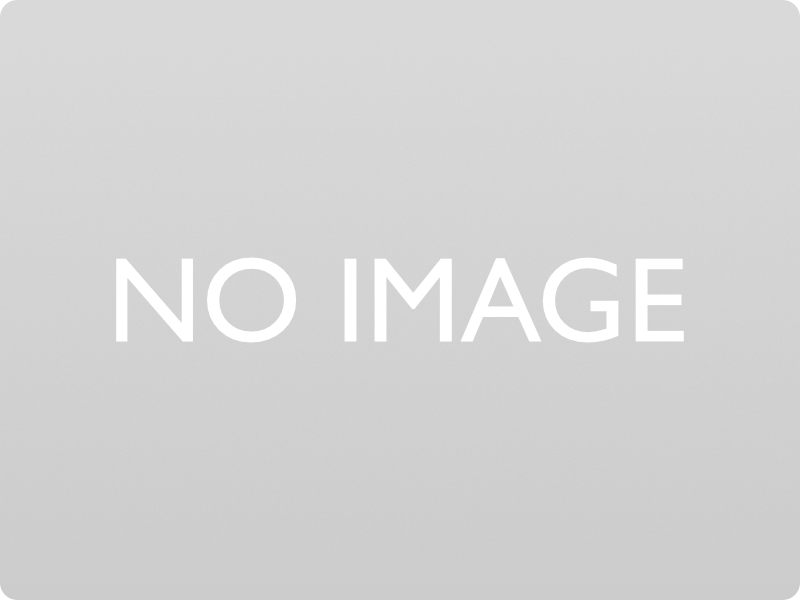【大久保藤五郎忠行とは】菓子職人から水道事業の責任者に
1590年、徳川家康は、豊臣秀吉の命により、それまで領有していた駿河・遠江・三河などを離れ関東に移り、江戸に本拠を置くことになりました。関東に新しい都を造るにあたり、家臣たちに分担して江戸の地を整えさせます。
伊奈忠次に利根川の整備を、新たな貨幣を橋本庄三郎に、そして人口が爆発的に増えた江戸へ命の飲み水を引く、水道事業を、もともと菓子職人として活躍していた大久保藤五郎へ一任しました。
今回は、そんな大久保藤五郎の奮闘を追って東京の町の歴史旅をご紹介します!
江戸の上水整備をまかされた 大久保藤五郎忠行とは
大久保藤五郎(本名は大久保藤五郎忠行)。その出生は記録に残っておらず、詳しいことはしられていません。
大久保家は、元は下野国(栃木県)の住人で宇都宮と名乗っていたそうです。越前などを経て三河にやってきて宇津と改名し、家康の祖にあたる松平信元に仕えたと『藩翰譜』に残っているのだとか。
そんな大久保家に生まれた藤五郎は、「菓子職人から水道事業の責任者へ」とうたわれていますが、もともと家康の小姓を務め、武士でした。
三河(現在の愛知県)で1563年に起こった一向一揆の針崎の戦いで身を挺して、主君である家康を守ろうとして受けた銃弾の傷がもとで、歩行が不自由になってしまいました。
20歳そこそこで自力で立ち上がることも、歩くこともできなくなってしまった藤五郎は、三河国上和田(現在の岡崎市)に引きこもってしまいます。
その時期から、菓子を作っては家康に献上するようになりました。なんともともと大久保藤五郎は菓子づくりが好きだったようです。
しかし、戦国時代の武将が、のほほんとしたお菓子作りを嗜む程度の趣味で、いきなり家康に献上し、職人になるというのは少し話が早すぎますよね。
家康にお菓子を献上し職人になるきっかけがありました。
それは戦です。
長い食糧もない極限状態の戦では、戦い以外でも生き残るのは厳しく、水が無い場合は、なんと死人の血も飲むほど。藤五郎はそんな状況を知っていたため、家臣の仙水清左衛門と熊井五郎左衛に菓子をもたせ、陣中見舞いに向かいます。戦に出られない身体となった藤五郎なりの貢献です。
家康は、大変喜び、兵たちにも配るようにいいつけ、藤五郎とその家来は長持ちのふたや菓子船に盛り分け、陣中の兵たちに菓子をふるまいました。
こうしたことから、江戸幕府の歴史を記した『徳川実紀』には、家康は大久保の作った菓子を大変気に入って、何度も作らせ献上させていました。なかでも駿河餅とよばれる餅。この餅は大久保主水家の由緒書などによれば三河餅となっています。
菓子職人から水道事業の責任者に抜擢された理由とは
1650年、家康が駿河・遠江・三河を離れ、関東に移ることになった際、江戸は入り江や低湿地が多く、井戸を掘っても良い水に恵まれない土地でした。そんな土地に移るとあって、これまでよりも多くの土地、水が必要になります。
そこでお声がかかったのが、晴れて菓子職人となった大久保藤五郎。
1590年の初夏の日、ついに水道事業の責任者となる日が来ます。
家康は家臣の大久保藤五郎に上水道の見立てを命じました。そもそもなぜ菓子職人から水道事業に任命されたのでしょうか。
菓子作りに長けている藤五郎であれば、菓子作りに大きく影響を与える水を見立てる力があると家康は考えたからだという説もありますが、詳しいことはいまだ解明されていないのだとか。
赤坂の溜池と小石川白台の河流を活用
藤五郎は家康の命を受け、早速、江戸に向かいます。
江戸湾沿いの集落へ赴き、漁師たちに何処の水が一等旨いかと話を聞いて歩きますが、なかなか見つかりません。
そして、約3ヶ月の苦闘の結果、藤五郎の舌に堪え得たのは、「赤坂の溜池」「神田明神山岸の細流」の2つ。
赤坂の溜池は、江戸城の南西方にあり、赤坂台地からしみ出した地下水が北へ流れ落ちて池をなしたもの。
神田明神山岸の細流は、江戸城の北東にあり、現在の駿河台の上に立っている原住民鎮守の神。この駿河台とその西隣の本郷台地の間にある小さな谷川でした。
前者の水を城の南西地域に巡らし、後者の水を北東地域に巡らせば、地域的な重なりがなく、江戸市中を効率的に網羅することができると考えた藤五郎は、早速とりかかります。
結果的に、藤五郎は3カ月という短期間のうちに水源を発見し、普請事業をやり終えます。
用水事業を命ぜられた藤五郎は、小石川(現在の後楽園のあたり)の流れを利用し、この水を小さな堀割で駿河台方面へと流しました。
さらに江戸の西にある武蔵野最大の湧水地である井の頭池、善福寺池を源に、それぞれの池から流れる河流を利用して、江戸城をはじめとして市中の引水を開発。この上水は小石川上水とよばれています。
これが、江戸の上水道の始まりと言われています。
小石川白台の河流を飲み水にする際、神田方向に通しました。この小石川白台こそ、後に神田上水と呼ばれる上水へと発展しています。
大久保藤五郎は、この功により、家康から「主水」の名を賜り、水は濁らざるを尊しとして「もんと」と読むべしと言ったといいます。以来、子孫は代々主水と称し、幕府用達の菓子司を勤めました。現在、台東区の瑞輪寺にある大久保主水の墓があります。
その近くにある八角形の井戸は、1835年に十代目が、忠行の業績を顕彰したものだとか。
赤坂と溜池山王を実際に旅してみました
さっそく歴史旅へ出発です!
大久保藤五郎の舌に堪え得たと言われる、「赤坂の溜池」「神田明神山岸の細流」の2つがあった場所と、のちの小石川上水のもとになる小石川後楽園をめぐってみたいと思います。
到着したのは赤坂駅。
大久保藤五郎が地元の人々への聞き込みで見立てた赤坂溜池のあった場所です。
溜池交差点の安全地帯には「溜池発祥の碑」がありました。
江戸時代の初期、江戸城の防備をかねた 外堀兼用の上水源として作られました。
近くには溜池山王駅が。
赤坂の溜池を利用して、江戸城の外堀に使用されました。
そのなごりが地名に残っているのですね。
溜池山王駅から永田町駅へ歩くと、赤坂見附跡があります。
赤坂見附跡とは、江戸城外郭門のひとつである赤坂御門の一部で、敵の進入を発見する施設であるため「見附」とも呼ばれていました。
最期に訪れたのは、水道橋付近にある神田上水の碑文。
碑文には、当時の上水の流れていた地図と、説明文がありました。
「井の頭池の湧き水を水源とする、江戸時代初期に造られた、日本最古の都市水道です」
現在の水道につながるもとになった神田上水。
東京の町にも、深い歴史が残されている印象的な歴史旅でした。
藤五郎が見つけた神田上水のもととなった溜池をめぐる歴史旅はいかがでしたか。
ちなみに、藤五郎はこの成果によって出世しませんでした。水道奉行を命ぜられたわけでもありませんので。禄を返上して幕府の御用菓子司として菓子屋を始めます。
御菓子司大久保主水には屋号がなく、「大久保主水」を店名に、十五代将軍慶喜の時代まで御用菓子司をつとめ、最後まで御用達菓子司筆頭の地位を降りることはなかったのだとか。